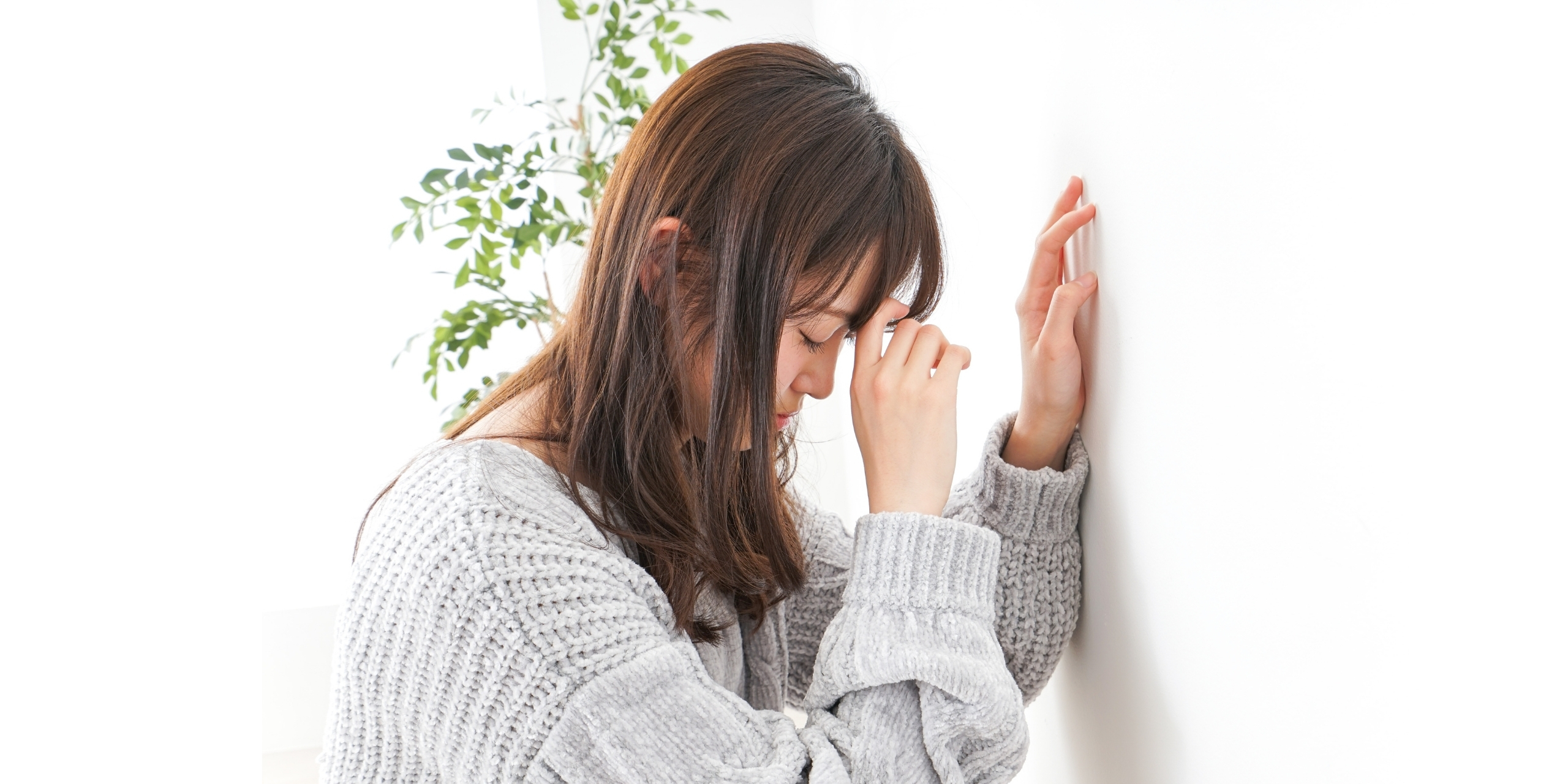
健診の結果に「貧血」と書かれていると、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
「自分は鉄分が足りないのかな?」
「放っておいても大丈夫なのだろうか?」
「大きな病気が隠れていないか心配…」
そんな思いで結果表を見つめる方も少なくありません。
岐阜市にある いろはなクリニック(内科・血液内科・小児科) では、健診で「貧血」と指摘された方に向けて、血液専門医が丁寧に診療を行っています。
この記事では、健診で「貧血」と指摘された時に知っておきたい基礎知識をまとめています。
- 貧血とはどのような状態なのか
- どんな原因や病気が考えられるのか
- 放置せずに確認すべきポイントは何か
- いろはなクリニックでできること
これらをわかりやすく解説しながら、「貧血」とうまく付き合うための第一歩をお伝えします。
貧血とはどんな状態?
貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビン(Hb)が基準値より少ない状態を指します。
- ヘモグロビン(Hb):酸素を運ぶ役割を持つたんぱく質
- 基準値(成人の場合の目安)
- 男性:13.0 g/dL 以上
- 女性:12.0 g/dL 以上
ヘモグロビンが少ないと、体の隅々まで酸素が届かず、疲れやすい・動悸・息切れ・めまいといった症状が出ることがあります。
また、慢性的な酸素不足により、イライラ・頭痛・肩こりなど一見すると貧血とは結びつきにくい症状が現れることもあります。特に女性では「生理があるから貧血は当たり前」と思い込んでいる方も少なくありません。しかし、貧血を改善することで日々の不調が軽減し、生活の質(QOL)が大きく向上するケースも多く見られます。
貧血の主な原因
一口に「貧血」といっても、原因はさまざまです。
- 鉄欠乏性貧血:最も多いタイプ。鉄分不足や出血(生理や胃腸からの出血)が原因。
- 巨赤芽球性貧血(ビタミンB12・葉酸欠乏):栄養不足や消化吸収の異常が関与。
- 溶血性貧血:赤血球が通常より早く壊れてしまう状態。
- 造血不全(再生不良性貧血、骨髄異形成症候群など):骨髄で血液がつくられなくなるタイプ。まれですが注意が必要です。
健診で貧血を指摘されたらどうすべき?
まずは再検査で原因を確認することが大切です。
- 追加の血液検査(鉄、フェリチン、ビタミンB12、葉酸など)
- 便潜血検査(消化管からの出血がないか確認)
- 必要に応じて胃カメラ・大腸カメラ
「疲れやすさ」「息切れ」「顔色の悪さ」が続く場合は、早めの受診がおすすめです。
いろはなクリニックでできること
当院では、
- 健診結果をもとにした再検査
- 鉄欠乏性貧血や栄養性貧血の診断・治療
- 食生活やサプリメントの活用を含めた栄養指導
- 必要に応じた専門医療機関(消化器内科・血液内科)への紹介
などを行っています。
「貧血」と一言で言っても、病態は様々です。放置せず、まずは原因をしっかり確かめることをお勧めします。
まとめ
- 貧血は「血液中の酸素を運ぶ力が不足している状態」
- 疲れやすさだけでなく、イライラ・頭痛・肩こりなどの不調の原因になることもある
- 特に女性では「慢性の貧血=当たり前」と思い込んでいるケースがあるが、改善することで生活の質が向上することが多い
- 健診で指摘されたら、再検査と原因の確認が大切
- 当院で気軽にご相談いただけます
健診で貧血を指摘された方は、お早めにご相談ください
